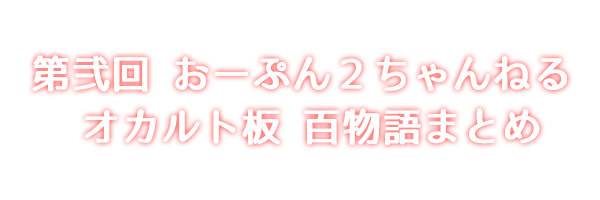第48話『街灯にまつわる話』@ 薄荷柚子◆CYOadRFefE 様
私の実家は堤防沿いにある。家の北側は堤防と川しかない。 夜になれば真っ暗なのに、明かりと言えば向かいの家の前にある街灯だけだ。 その街灯も今時珍しい、木の電柱に傘と電球が付いているだけの物で、まったく心もとない。 近所でこんな古びた街灯はここだけだった。 数年前の話だ。夜9時頃家に向かう一本道を歩いていると、向かいの街灯の下に人がしゃがんでいるのを見かけた。 この一本道は堤防で行き止まり、しかも袋小路になっている為、 近所の人か堤防に用事のある人しか利用しない。誰だろう?と思いながら距離を縮めた。 近くで見るとその人物は知り合いではなかった。 首元ぐらいの長さの髪に地味な服装、中肉中背。 こちらに背を向けている為、男か女かまったく分からない。 片膝を付いて、微動だにせず堤防の暗闇を見つめている。 こっそりと家に入った私は母を呼んで、街灯の下の人物を見せた。 同じ場所で堤防を凝視し続けるその姿は、何かを待っている様にも見える。 怖くなった母は、向かいのM家に「お宅の前に不審者がいる」と連絡を入れた。 驚いたM家の旦那さんが外に出たところ、もう不審者はおらず、街灯の下にサンダルが揃えて置いてあったという。 話は近所に広まり、それからしばらくは皆、川で亡くなった人がいないか新聞記事を注意していた。 結局川で亡くなった人はいなかったが、不審者を見かけてから2ヶ月ほど後、何者かにより街灯の下に花が供えられていた。 白花メインのバスケットアレンジはとても豪華で、到底いたずらで置くレベルの物ではない。 M家では気味悪がって「迷惑になりますので持ち帰って下さい」と張り紙をしたが、一向に無くならない。 結局花が枯れた頃、M家で処分する事になった。 すると数日後にはまた新しい花が供えられている。そんな事が3度繰り返された。 3度目の花を処分した後、犯人は捕まった。 M家の息子さんが早朝に帰宅した際、偶然にも花を供える現場を目撃したのだ。 犯人は小柄で白髪の老女だったという。どうやら私と母が見た人物とは別人らしい。 花を供えた理由を聞いても「ここに娘がいる」と言うばかりで要領を得ない。 それでも根気よく聞き出すと、娘さんは数年前に病死したらしい事、 拝み屋の様な人に「娘さんがこの街灯の下にいる」と言われたらしい事が分かった。 (肝心の、何故この街灯の下なのか?については解明されなかったが。) 老女はどうも認知症を患っているようだったので、M家では大事にはせず 花を供えないよう説得して、そのまま帰したそうだ。 その後この街灯に花が手向けられる事は無くなった。 そして3ヶ月ほど前、行きつけの店の主人からこんな話を聞いた。常連客の体験だという。 その女性はウォーキングが趣味で、堤防が定番コースだった。 ある日歩き始めが遅くなり、折り返し地点に来た頃には日が落ちてしまった。 歩きなれた道とはいえ、夜の堤防を歩くのは怖い。そこで堤防を降りて、住宅街を抜けて帰る事にした。 住宅街に入るとすぐ街灯が見えた。古びた木の街灯だったけれど、明かりがあるだけでほっとしたという。 ここまで聞いて予感がした私は、その街灯の事を詳しく尋ねた。果たしてそれは、件の街灯であった。 実家の向かいにある街灯だと分かり、店主と二人驚く。更に店主が語るところによると… 女性が街灯の下を通り過ぎたその時、急に明かりが揺れ出した。 丁度それは、大きな蛾が群がっているような光の明滅だったという。 振り返ると、街灯の下に何かがぶら下がっている。眩しくて見づらいため一、二歩戻ったが、異様な光景に足を止めた。 ぶら下がっていたのは、麻袋に入った人だった。 頭部は袋から出ているが、長い髪を振り乱して顔は見えない。 その人は街灯が揺れるほど必死にもがいている。反射的に助けなければと思ったが、 先ほど堤防から降りた時には、こんな物を見た覚えがない。 しかしあまりに生々しいので、夢とも現とも判断がつかず、ただただ見上げていたそうだ。 麻袋を下げてあった紐が千切れたのか、地面に人が叩きつけられる音で、女性は我に返った。 自分の2mほど前に落ちているそれは明らかな質量を持つ“この世のもの”にしか見えない。 やはり助けなければ、そう思った女性の目の前で、麻袋からうつ伏せに人が這い出して来た。 その女性は「ぬるり」と表現していたそうだ。とにかく人の動きではなかった、と。 それは一瞬にして女性の足元に到達していた。 2mは離れていたはずなのに、今は女性の爪先に額を預けている。 質量はあるが、この世のものかと問われると… 女性は全速力でその場から逃げ出したそうだ。 今後もあの街灯の下で奇妙な事が起こるのか、楽しみでもあり恐ろしくもある。 とりあえずもう自分は体験したくないので、夜間は近づかないようにしているのだが。